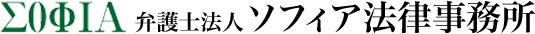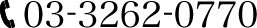労務問題のQ&A
労働時間
Q1 副業と懲戒処分・時間外手当
A社は、従業員に対して、兼業を禁止しています。A社の始業時間は9時で、終業時間は18時(休憩時間1時間)です。この度、従業員Xが終業時間後にB社で兼業を始めたことが判明しました。A社は、兼業禁止規定の違反としてXを懲戒処分とすることはできますか。A社とB社の労働時間を通算すると法定労働時間を超えますが、A社とB社のどちらが時間外労働手当を支払う必要がありますか。
A1
兼業禁止規定に違反したのみでは懲戒処分はできません。
労働時間を通算して法定労働時間を超える場合、原則として後から雇用契約を締結したB社が時間外手当を支払う義務があり、A社にはありません。
<解説>
1.兼業禁止規定違反と懲戒処分
就業規則で「会社の許可なく社外の業務に従事しまたは自ら事業を行ってはならない。」と規定し、これに違反した場合を懲戒事由に定めていることがあります。しかし、従業員の職場外の職務以外の行為については私生活の自由や職業選択の自由の要請があることから、兼業の懲戒事由該当性は厳格に判断する必要があります。裁判例からみると、兼業許可制の規定が合理的に定められている場合であっても、次のような場合が違反類型とされています。
①同業他社等の競業関係にある企業で就労する場合
②自社の就業時間と両立しない就労をする場合
③就業時間外または休日において継続的に相当時間就労することにより自社に対する労務の提供に支障が生じる場合
したがって、正社員が終業時間後に兼業を行った場合、上記の①から③の事情があれば、不許可とすることができるが、そうでない場合は兼業禁止規定違反とはなりません。その場合に無許可兼業を理由とする懲戒処分を行えば、懲戒処分は権利濫用により無効となります。
2.兼業と時間外手当
厚労省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&Aでは、一般的には、通算により法定労働時間を超えることになる所定労働時間を定めた労働契約を時間的に後から締結した使用者が契約締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきことから、時間外手当の支払義務を負うことになるとしています。
したがって、本件では、B社が時間外手当の支払義務を負うことになります。
就業規則
Q2 就業規則作成・変更に関する意見書
会社が就業規則の作成や変更をする場合、使用者は当該事業場の過半数代表(過半数組合、これが存在しない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴取しなければならないとされている(労基法90条1項)。そこで、労働者の過半数代表者に意見を聴取したところ、過半数に満たない組合の代表者と連名で作成した意見書を提出してきた。受理しなければならないか。
A2
受理する必要はなく、労働者の過半数代表の意見を記した書面の提出を求めることができる。
<解説>
1.就業規則の作成や変更をする場合、当該事業場の過半数代表の意見を聴取する必要があり、就業規則届出の際には、過半数代表の意見を記した書面を添付する必要があります(労基法90条2項)。
したがって、過半数未満の組合の意見を記した書面の添付は義務付けられていませんし、また、当該組合も使用者に対して当該書面の提出を主張しうる権利もありません。
2.仮に、過半数代表と過半数未満組合の意見が同じであったにしても、当該書面に過半数未満組合の名義を出す理由はありません。もとより、過半数未満組合が、当該書面以外の書面で使用者に対して意見を表明することは自由ですが、就業規則届出の際に添付する必要がある書面として受領を強制されるものではありません。
3.使用者が、過半数代表とともに過半数未満組合の名義の書面の提出を黙認していると、組合の既得権として、使用者がこれを認めたことになり、今後、過半数未満組合の同意なく変更できなくなる可能性があることに注意すべきです。
Q3 有期契約社員の無期転換申込権と高年齢者雇用安定措置
有期雇用契約社員が無期転換権を行使した。
無期雇用の契約社員の就業規則では60歳定年を定めているが、それ以降の規定がない場合でも、定年後65歳までの雇用義務があるか。
A3
事業主は、65歳までの雇用義務ではなく、65歳までの高年齢者雇用安定措置を講ずる義務があり、その不履行で不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
<解説>
1.無期転換後の労働条件
無期転換後の労働条件は、当事者の契約関係において別段の定めがない場合には従前と同一とされ、有期契約当時のものを引き継ぐとされています(労働契約法18条1項)。
本件では、無期雇用の契約社員の就業規則があるので、これが「別段の定め」となり、無期転換者の労働条件は就業規則に従って定まります。
2.高年齢者雇用安定法
高年齢者雇用安定法第8条は、事業者が労働者の定年の定めをする場合、「当該定年は60歳を下回ることはできない」と規定しています。
また、同法第9条は、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、当該定年の引上げ、現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を引き続き雇用する制度(継続雇用制度)の導入、当該定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければならないと規定しています。
3.本件の回答
そこで、本件でも事業主は、高年齢者雇用安定法に従い、65歳までの高年齢者雇用確保措置を講ずる義務があります。事業主が、この措置を講じなかった場合、指導、助言、勧告及び企業名公表といった公法的制裁の対象となります(高齢者雇用安定法第10条)。
つまり、高年齢者雇用安定法第9条には、労働者が継続雇用制度の導入請求権を行使できるという意味での私法上の効力はありません。事業者が高年齢者雇用確保措置を講ずることなく、定年を理由に労働者を60歳で退職させた場合、退職の効果が直ちに否定されるものではありません。
ただし、不法行為による損害賠償責任が生じる余地はあります。その場合でも高年齢者雇用安定法第9条違反の事実だけでは足りず、事業主の故意・過失、損害の発生、因果関係等の不法行為の成立要件を充たすことが必要です。
Q4 65歳以上の継続雇用制度
当社は、社員の定年を65歳としています。65歳以上の継続雇用制度はありますが、会社は、今年定年となるAを継続雇用することは予定していません。会社が継続雇用しないことは可能でしょうか。
A4
65歳以上の再雇用制度規程に定める継続雇用しないことができる事由に該当する場合は、継続雇用しないことができる。
<解説>
1.65歳までの雇用確保措置
高年齢者雇用安定法第9条は、65歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳までの雇用確保の措置として、次のいずれかの措置をとることが義務付けられています。
ア.当該定年の引上げ イ.継続雇用制度 ウ.当該定年の定めの廃止
ただし、イの継続雇用制度を採用する場合、心身の故障のため業務の遂行に堪えられない者、勤務状況が著しく不良で従業員としての職責を果たし得ないこと等の解雇退職事由に該当する者は継続雇用しないことができるとされています。
2.65歳以上の継続雇用制度
それでは、65歳以上の高年齢者の継続雇用の現状はどうでしょうか。
高年齢者雇用安定法第10条の2は、65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業主は、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用確保の措置として、次のいずれかの措置をとることが努力義務とされています。
ア.当該定年の引上げ イ.65歳以上の継続雇用制度 ウ.当該定年の定めの廃止
したがって、現時点(令和5年4月)で、65歳以上の継続雇用制度等の措置を講じていなくとも、法的に問題は生じないと思われます。
3.既に65歳以上の継続雇用制度を採用している場合
当該運用に当たっては、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針が参考になります。
継続雇用しないことができる事由としては、65歳までの継続雇用制度と同様に、心身の故障のため業務の遂行に堪えられない者、解雇退職事由に該当する者の外に、継続雇用しないことができる事由を就業規則に定めることができるとしています。ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められるとされています。
4.本件の回答
会社が恣意的な人選でAについて継続雇用しないことは違法ですが、前記のとおり、心身の故障のため業務の遂行に堪えられない者、解雇退職事由に該当する者以外でも、就業規則に定められた継続雇用しないことができる事由にAが該当するのであれば、継続雇用の対象から除くことは可能となります。
解雇・退職
Q5 試用期間
当社では、就業規則で試用期間を3ヶ月として、試用期間中に社員として不適格と判断された者は本採用をしないと規定されています。この度、試用期間中の社員で、「正当な理由なく無断欠勤を3日」続けた者がおりました。これを理由に本採用しないと判断することはできますか。
A5
無断欠勤を3日間継続したことを理由として本採用しない(=解雇)ことは、相当性を欠き、違法とされる公算が高い。改善の機会を与えても無断欠勤を反復する場合は、本採用拒否が正当と判断される可能性が高い。
<解説>
1.試用期間の位置づけ
試用期間は、新入社員の従業員としての適格性を判断するための期間であり、OJTによる判断で、不適格の従業員を解雇する制度です。本件で本採用しないといっているのは、会社による解雇を意味します。
2.試用期間の長さ
試用期間は一般的に3ヶ月から6ヶ月とされることが多いようです。試用期間の長さには法規制はありませんが、試用期間は従業員の地位が不安定であることから、合理性のない期間は公序良俗違反として無効とされます。
3.従業員の適格性の判断
試用期間中でも従業員と使用者間には労働契約が成立していますが、従業員の適格性判断の期間であることから、使用者に通常の解雇よりも広い解約権が与えられています。法的には、試用期間は、解約権が留保された労働契約であり、本採用拒否は留保された解約権の行使です。
したがって、留保された解約権の趣旨に合致する客観的合理性と相当性が必要となります(労契法16条)。
具体的には、試用期間中の勤務等により、使用者が当初知りえなかった事実が判明し、今後の雇用継続が不適当と判断されることが必要です。
4.無断欠勤3日について
試用期間は適格性判断の期間ですが、そもそも適格性を判断する期間として3日は短すぎます。
また、無断欠勤3日で将来の雇用継続において大きな支障になると判断することも困難です。
試用期間は、適格性の判断期間であると同時に新入社員に対する教育の期間でもあります。
新入社員の勤務態度の不良に対しては、使用者による教育指導により、その改善を図る機会を与えるべきです。
使用者が教育指導をすることなく、無断欠勤が3日続いたことのみを理由として本採用を拒否した場合、解雇の相当性を欠くとして、違法とされます。
Q6 合意解約の申し入れ
A社員から、6月30日を退職日とする自己都合退職届が提出されました。本人は、4月末までは出社し、5月の連休明け以降は、未使用の有給休暇を消化したいとの意向です。有給休暇は6月22日で全て消化してしまいますが、本人は6月23日から退職日までは欠勤を希望しています。会社は、このような退職届けを受理しなければならないでしょうか。
A6
当然に受理する必要はありません。合意解約の申し入れと考え、受理をせずに、退職日の変更を話し合って合意すべきです。
<解説>
1.退職届の意味
退職届には、3種類があると考えられます。
①労働者による一方的な解約(辞職)の通知
②労働者からの合意解約の申し入れ
③使用者からの合意解約の申し入れに対する承諾
但し、本件は使用者からの解約申し入れはないので、③には該当しません。
2.一方的な解約(辞職)の通知(①)と合意解約の申し入れ(②)の区別基準
当事者は円満な合意による退職を求めるという一般原則によれば、労働者が使用者の同意がなくとも退職したいという強い意思をもって退職届を提出している場合を除き、合意解約の申し入れと考えるべきです。
判例(広島地判昭60.4.25)も同様に判示して「今月いっぱいで辞めさせていただきます」との発言を合意解約の申し入れとしています。
3.本件の回答
本件でも、A社員からの退職届を合意解約の申し入れと理解すべきでしょう。A社員の退職届は確定的に雇用契約を終了させる意思表示というよりは、退職日まで有給休暇を使い、それで足りず欠勤が生じる場合、会社はこれを受け入れて、退職日までの従業員の地位を保証してほしいとの合意解約の申し入れと解釈できるからです。
A社員による合意解約の申し入れと考えると、会社が6月23日から退職日までの欠勤を容認することは困難で、会社がこの申し入れを拒否することは可能です。退職日の変更を提案して、新たな合意解約の成立を模索すべきです。A社員が会社の提案に応ぜず、上記の予定を強行する場合、やむを得ず、会社がA社員を解雇することも考えられます。
Q7 有期雇用社員の中途退職の申出
当社の有期雇用社員Aから、契約期間途中(契約期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日)に、同じ勤務時間で、もっと条件が良い転職先が見つかったことを理由に、退職の申出をしてきました。
・会社は、Aの退職の申出を拒否することは可能でしょうか。
・Aが強引に転職した場合、会社は、どのような対応を取れますか。
A7
会社は、Aの退職の申出を拒否することができます。Aが強引に転職した場合、会社はAを解雇して、損害賠償を請求することができます。
<解説>
1.労働者の辞職の自由
労働者の辞職について、使用者は、原則的にこれを制約することはできません。ただし、労働者が全く自由ということではなく、民法上の規制があります。
2.民法628条「やむを得ない事由」
当事者が期間の定めがある雇用契約を締結した場合、当事者はこの合意に拘束されて、その期間内は契約からの離脱は原則として認められません。
しかし、「やむを得ない事由」が認められる場合は、労働者は契約の解除をすることができます。「やむを得ない事由」とは、当該契約期間の満了を待つことなく直ちに雇用を終了せざるをえないような特別の重大な理由をいい、例えば、労働者が病気等で長期間就労ができない場合、使用者の賃金未払いや労基法違反で就労が困難な場合などです。
Aは、契約期間が1年であるにも関わらず、期間途中に好条件の転職先が見つかったという理由で退職の申出をしていますが、この理由は、期間満了を待てないほど特別で重大な理由には該当せず、Aは自由に契約を解除することはできません。
したがって、会社はAの退職申出を拒否することができます。
3.労働契約法17条
労働契約法17条は、期間の定めがある労働契約につき、使用者は「やむを得ない事由」がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで、労働者を解雇できないと規定しています。それでは、本件でAが強引に転職した場合、会社はどのような対応が可能でしょうか。
この場合、Aの過失による長期不就労が発生することから、「やむを得ない事由」が認められ、会社はAを解雇することができるとともに、代替社員を確保するために要した費用相当額の損害賠償を請求することができると考えます。
4.なお、Aの雇用期間が1年を超える期間と契約されていた場合、前記民法628条の規定に規制されることなく、1年を経過すれば、Aは退職することができます(労働基準法附則137条)。
Q8 試用期間の延長
・中途採用した社員が、6ヶ月の試用期間のうち3ヶ月を経過した後、怪我のため3ヶ月近く欠勤していますが、もうすぐ復職可能な見込みです。復職後に試用期間の延長を考えていますが、可能でしょうか。
・延長する試用期間はどのくらいが妥当でしょうか。
・復職後の業務内容を欠勤前の業務と変更することは可能でしょうか。
A8
試用期間の延長は、就業規則等の根拠規定に基づき行うことが必要。本件では、3ヶ月以内が妥当。
復職後の業務を欠勤前の業務と変更することも可能。本人から同意書を得ておくことが望ましい。
<解説>
1.試用期間とは、新採用者を正社員として本採用するに足りる職務適格性を有するか否かを判断するための期間であり、その間に職務不適格と判断された場合には解雇することができる解雇権が留保された期間であると解されています。
試用期間の目的が本採用の可否を決定するために職務適格性を観察するためであるとすると、使用者が試用期間と定められた期間を任意に延長することはできません。
2.試用期間の延長は、就業規則上の具体的な定めなど契約上の明確な根拠がない限り、延長することはできないとされています。そして、試用期間の趣旨に照らせば、試用期間満了時に一応職務不適格と判断された者について、直ちに解雇の措置をとるのでなく、配置転換などの方策により更に職務適格性を見いだすために、試用期間を引き続き一定の期間延長することは許されると解されます。
本件では、就業規則に試用期間の延長の定めがあるとしたうえで、試用期間中の怪我により採否の判断ができないという相当な事情が認められるので、試用期間の延長が認められます。
3.試用期間の延長期間としては、復職後の業務が欠勤前の業務と同一である場合、試用期間の残りの3ヶ月とすることが妥当と考えます。試用期間が新採用者にとって不安定な期間であることを考えると長期間の延長は望ましくなく、使用者も試用期間とされている6ヶ月内で採否の判断をすべきでしょう。
4.試用期間満了時に一応職務不適格と判断された者を直ちに解雇とするのでなく、配置転換などの方策により更に職務適格性を見いだすために、試用期間を延長することは可能です。そのため、復職後の業務内容を欠勤前の業務と変更することは可能です。
ただし、試用期間の延長期間に、配置転換により業務内容が変更するため、試用期間延長の理由と延長期間を本人に説明したうえで、本人から同意書を徴求しておくことが望ましいでしょう。
Q9 試用期間満了時の本採用拒否と解雇予告手当
A社は、試用期間を6か月と定めています。Bは令和5年2月に入社。3月から7月まで私傷病で欠勤しました。そこで、A社は、Bの試用期間を令和6年1月末まで延長しました。Bは、令和5年8月は出社しましたが、9月から再び欠勤をはじめ、10月は実労働日21日、11月は実労働日2日、12月は実労働日0でした。令和6年1月に入り、A社は、Bを本採用しないことに決定しましたが、解雇予告手当はどう算定したら良いでしょうか。
A9
労基法20条1項は、労働者の解雇に当たり、30日前に予告しない場合は「30日分以上の平均賃金」を支払わなければならないとしています。
試用期間中の者の解雇については、14日以上引き続き使用されていた場合は、通常の解雇と同様に少なくとも30日前の予告か30日分以上の平均賃金の支払いが必要です(同法21条4号)。
同法12条が「平均賃金」の算定につき定めているので、同条の規定に従い、以下のとおり、「30日分以上の平均賃金」を算定します。
<解説>
1.原則的な算定方法
労基法12条1項では、「算定事由の発生日以前3か月間における賃金の総額」を「その期間の総日数」で除して算定するとされています。
そこで、10月分賃金と11月分賃金の総額を10月から12月までの総日数で除して算定することになります。
2.除外期間・賃金について
同条3項は、休業などで賃金の総額が極端に減少した場合や臨時の賞与などで賃金が異常に多くなった場合は、算定基礎の期間や賃金額から、除外することが必要とされています。そして、5号には「試みの使用期間」があげられています。しかし、試みの使用期間に算定事由が発生したときは、その期間中の日数及び期間中の賃金は、前項の期間並びに賃金の総額に参入するとされています(労基則3条)。
3.最低限の保障
平均賃金の算定期間内に自己都合の欠勤が多く賃金が異常に少なかった場合には、最低限の保障がされています(同条1項但書)。そして、労働契約での賃金の定め方により、下記の①場合と②の場合が考えられます(昭和30・5・24基収1619号)。
記
①10月~12月の3か月の賃金総額÷実労働日数×0.6
と欠勤含め実際の勤務ベースで算出する方法
②10月~12月で欠勤しなかったらもらえる賃金÷所定労働日数×0.6
で算出する方法
年休
Q10 年次有給休暇の時間単位取得
時間単位の年次有給休暇制度を導入しています。年休での1日の時間数は8時間としています。
①7時間の年休取得を請求する労働者に1日単位の年休に変更させることは可能ですか。
②労使協定で、取得できない時間帯を定めることはできますか
A10
①時季変更権の行使に当たらず、認められない。
②時季変更権の行使は個別的に検討されるので予め労使協定に定めることはできない。
<解説>
1.事業場の過半数代表との労使協定に基づき、1年に5日の範囲内で、年休の時間単位の取得が認められます(労基法39条4項)。
2.事業場の過半数代表との労使協定で定める内容は次のとおりです(労規則24条の4)。
(1)時間単位の年休を与えうる労働者の範囲
(2)時間単位の年休として与えうる年休の日数(5日以内)
(3)年休の日数について1日の時間数(1日の所定労働時間を下回らないことが必要)
(4)1時間以外の時間を単位として年休を与える場合はその時間数(1日の所定労働時間に満たないことが必要)
3.時間単位の年休も使用者の時季指定権の対象となります(労基法39条5項)。
しかし、設問①のように時間単位の年休取得の請求に対して、時間単位で時季変更するのでなく、1日単位での年休の取得に変更することは、時季変更には当たらず、認められません。
4.使用者は、年休取得の請求に対して、事業の正常な運営が妨げられる場合に時季変更権を行使できます。
しかし、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、労働者の具体的な年休請求に対して個別具体的に客観的に判断されるものですから、予め労使協定で、取得できない時間帯を定めること、所定労働時間の途中の時間単位年休の取得を制限すること、1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められません。
健康
Q11 コロナ感染症とワクチン接種の義務付け
当社は、食品関連の業務をしており、デパートの食品売場や商業施設に従業員が出入りしています。取引先からはワクチン接種済みの従業員の出入りを強く希望されています。そこで、従業員に対し、ワクチン接種を義務付けることは可能でしょうか。また、ワクチン接種に応じない従業員を配置転換することは可能でしょうか。
A11
従業員の意思にかかわらず、ワクチン接種を義務付けることはできないが、業務上の必要性から、ワクチン接種を行わない従業員を配転することは可能。
<解説>
1.日本経済新聞によると、コロナウイルス感染者のうち、2回ワクチン接種を受けた後の感染者の割合はワクチン未接種者感染者の15分の1とのことです。したがって、貴社が顧客・取引先に対して安心感を与えるために従業員に対するワクチン接種の義務化をお考えになることは、尤もと思われます。
2.予防接種法はコロナワクチン接種にも適用されますが、接種を受けるか受けないかは国民の意思によるとされており、予防接種の対象者は、予防接種を受けるべき努力義務があるとされ、必ず接種しなければならないとはされてはいません。アレルギー体質や副反応による健康被害等から接種を希望しないのであれば受ける必要はありません。
したがって、使用者が就業規則でコロナワクチン接種を義務付けることはできません。
3.しかし、ワクチン接種の努力義務は認められているので、使用者は、一定の節度を持って、ワクチン接種をすることを勧奨することは可能です。
従業員が使用者の勧奨にしたがって、自らの意思でワクチン接種をうけることに合意した場合は違法となるものではありませんから、貴社も従業員の合意を得てワクチン接種を受けてもらうことが適切な対応と考えます。
ただし、従業員がワクチン接種を拒否する明確な意思を表示したのに勧奨を継続することは、自己決定権の侵害として違法とされる恐れがあることから注意が必要です。
4.それでは、従業員がワクチン接種を拒否する場合、配転命令権のある使用者が当該従業員を配置転換することは可能でしょうか。
最高裁東亜ペイント事件判決(最二小判昭和61.7.14)は、配転命令権の行使が権利濫用に当たる場合として、①配転命令に業務上の必要性がない場合、または業務上の必要性がある場合でも、②他の不当な動機・目的をもってされた場合、もしくは③労働者に通常甘受すべき程度を著しく超えた不利益を負わせるものであるときを挙げています。貴社の配置転換は、ワクチン接種を受けていない従業員との接触でクラスター等の発生を防止したい取引先の強い希望によって行うものですから業務上の必要性は強く、①の要件は充たすと考えます。②の要件について、ワクチン接種を受けないことを理由にする不利益処分であるとして処分の無効を主張する見解があります。しかし、貴社の配置転換は、ワクチン接種を受けないことに対する報復といった不当な動機・目的を持ったものではありません。③の要件についても、当該従業員に対する配置転換が、職業上ないし生活上、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでない限り、権利濫用とはいえません。
したがって、貴社が、本件に関して配置転換により、取引先に対応することは十分に可能と考えます。
Q12 コロナ感染症とテレワーク
新型コロナウイルス感染症(無症状の場合)で自宅療養中の従業員がテレワークで業務をすることは可能か。
A12
主治医や産業医の意見を踏まえてテレワークを命じることは可能と考える。
<意見>
感染症法18条2項によると、新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者は、厚生労働省令で定める業務に、感染のおそれがなくなるまでの期間従事してはならないと規定しています。感染のおそれがあるので「業務に従事してはならない」という趣旨は、感染防止の点から職場への出勤を禁止するという意味と理解できます。
しかし、テレワークにより職場への出勤と業務への従事の結びつきが切断されると、職場に出勤せず、業務に従事することが可能となります。
そうであれば、新型コロナウイルス感染症を発症していても無症状の場合には、テレワークによる業務に従事することを命じることは可能となります。
ただし、会社が無制限に業務を命じることはできません。
新型コロナウイルス感染症による心身の負担には個人差があることから、テレワークによる業務を命じるに当たっても業務によって症状を悪化させること等がないように主治医や産業医等の意見を踏まえて従業員に過度な負担とならないように配慮した業務内容とすることが安全配慮義務の観点からも必要です。
Q13 健康情報
A社員から会社に入院のため1ヶ月間欠勤するとの申し出がありました。
総務課長がA社員に対して就業規則に基づき医師の診断書を提出するように命じたところ、A社員は「病名を知られたくない。個人情報だから応じられない。」と提出を拒否しました。
会社は、就業規則違反としてA社員に懲戒処分を行うことができるでしょうか。
A13
懲戒処分を行うことには相当性がなく、処分が違法とされる可能性がある。
<解説>
就業規則で1週間以上欠勤する場合には医師の診断書を提出するように命じている規定があります。
これは、会社の安全配慮義務の観点から、規定されていると解釈することができます。つまり、会社が社員の病状を把握して、欠勤明けに出勤した社員の就労につき、具体的にどのような配慮が必要かを検討する必要があるからと考えることができます。
他方、病名などの健康情報は、不利益や差別につながるおそれのある機微な情報であり、個人情報保護法2条3項は、これを要配慮個人情報としています。同法20条2項〈改正法〉は、要配慮個人情報は例外を除き、予め本人の同意を得ずに取得することが禁止されています。
したがって、医師の診断書を提出については、本人の任意提出を原則として対応し、提出しない場合にも就業規則違反として懲戒処分をすることは避けるべきでしょう。
なお、本人に対して診断書の任意提出を促すに当たっては、使用目的を特定することや診断書を取り扱う者を人事部に限定するなどして、直接の上司に関与させないことを説明すべきでしょう。
また、任意提出を促したにもかかわらず、本人が医師の診断書を提出しない場合は、欠勤明けの出勤について、使用者の安全配慮義務は軽減されると考えられます。
福利厚生
Q14 社宅の立ち退き
会社は、所有者から社宅として賃貸した部屋を社員Aに有料で使用させていたが、所有者から建物の老朽化に伴う立ち退き請求を受け、立退料43万4000円の支払と引き換えに立ち退きに合意した。
Aは引越費用として25万円を支出した。Aは、本件立退料を受け取ることができるか。引越費用はA負担か。
A14
会社が立退料を受け取ることができる。Aは会社に対して引越費用の支払を請求できる。
<解説>
1.社宅の法的性質
会社と社員との社宅の使用関係は画一的に決定されるものではなく、その契約の趣旨によって決まります。社宅の使用料が通常の家賃相場と同等であれば、社宅契約は賃貸借契約とされる傾向にあります。
これに対して、社宅の使用料が通常の家賃相場より相当低額である場合は、社員に対する福利厚生策の一環として、社宅管理規程によって規律される無名契約とされます。その場合は借地借家法の適用はないとされています。本件では、使用料の額は不明ですが、社宅は相場の賃料よりも低いことが通常ですので、無名契約を前提として説明します。
2.立退料はAが取得するのか。
現実に立退くのはAですから、Aが立退料を取得してもよいようにも思えます。
しかし、所有者と賃貸借契約を締結したのは会社であり、契約上立ち退き義務と立退料が対価関係に立つことから、立退料を取得するのは会社です。
Aは、所有者との関係では、直接の契約関係には立たず、会社の履行補助者の扱いとされます。
したがって、Aは所有者に対して立退料を請求することはできません。
また、Aと会社の関係は、社宅管理規程で規律されることから、同規程に立退料につき定めがある場合以外は会社に対しても立退料を請求することはできません。
3.引越費用はAの負担か。
Aと会社の関係が社宅管理規程で規律されることを前提とすれば、引越費用の負担も社宅管理規程によることになります。
それが明確ではない場合は、会社が立退義務を負うことから、引越費用も会社が負担すると考えるべきでしょう。
実質的にも、本件は、①Aが任意で立退いたケース、②Aに帰責性があり立退きを要求されたケースのいずれにも該当しませんので、Aに引越費用を負担させることは理由がないと考えます。
したがって、Aは会社に立替えた引越費用の返還を請求することができます。
労働者の人格的利益
Q15 犯罪歴とプライバシー
A社員は、入社前に放置自転車を勝手に使用して略式命令により罰金刑を受けました。会社はその事実を知りませんでした。
しかし、入社から既に15年以上経過しており、仕事ぶりは極めて真面目で、この度、会社はA社員を部長候補者としました。
ところが、社員の一人から、犯罪をおかした人を部長にすることはおかしいとの投書があり、A社員の実名入りの新聞記事コピーが送られてきました。
会社がA社員に事実関係を確認することは可能でしょうか。また、A社員は懲戒処分の対象となるのでしょうか。
A15
A社員に事実関係を確認することは可能。
A社員に懲戒処分を行うは相当性がなく、処分が違法とされる可能性が高い。
<解説>
1.A社員にはプライバシーをみだりに公表されない権利があり、不当な侵害に対しては不法行為が成立するとされています。しかも、犯罪歴などの情報は、本人の不利益や差別につながるおそれのある機微な情報であり、個人情報保護法では要配慮個人情報(2条3項)として、取り扱いに特に配慮を要するとされています。他方、雇用関係は使用者と労働者の相互の信頼関係を基礎に置く継続的契約関係です。
したがって、使用者は、労働力の評価に直接関わる事項や企業秩序維持に関係する事項等で個人情報の取得が必要となることがあります。本件でも、会社はA社員を部長に昇格させるかを決定する必要があり、その適格性を判断するために、A社員の個人情報を取得することは、目的として相当と言えます。ただし、取得の方法も相当であることが求められ、A社員の昇格判断に必要かつ合理的な範囲で調査し、申告を求めることは許されると考えます。
2.A社員は、入社にあたり、賞罰につき申告しなかったことが推測されます。このような経歴詐称を理由に、現時点で、懲戒処分の対象とすることができるでしょうか。
会社が入社に当たりA社員に賞罰の申告を求めていなければ、経歴詐称にはなりません。申告を求めていたとして、経歴詐称が懲戒事由となるためには、重要な経歴詐称であること、使用者との信頼関係を破壊するものであることが必要です。犯罪歴の詐称は、重要な経歴詐称に当たると考えますが、略式命令による罰金刑であり、既に刑の言い渡しが効力を失っていること、入社から15年間真面目な仕事ぶりが評価されて要職の候補にまでなっていることを考慮すると会社との信頼関係が破壊されている様子はなく、懲戒の必要性・相当性は認められないと考えます。
したがって、本件を理由として、A社員に懲戒処分を科すことはできないと考えます。
採用
Q16 採用の事由の制限
・私立学校で養護教員の補助者を募集することになりました。
・仕事内容から、女性で年齢は50歳未満の方を募集したいと思いますが、問題があるでしょうか。
A16
労働者の募集・採用に当たり、「女性のみ」を対象とすることや募集対象の年齢を一定範囲に限定することは違法とされるので、避けるべきです。
<解説>
1.「募集・採用に当たり、「女性のみ」を対象とすること」について
男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます)5条は、性別を理由とする差別の禁止につき「事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と規定しています。均等法10条に基づき定められた指針には、均等法5条で禁止される措置につき具体的に例示されています。そして、募集採用にあたり、その対象から男女のいずれかを排除すること(女性のみを採用の対象とする場合も含まれます)は均等法5条に違反するとされています。均等法5条に違反しても、強制的に労働契約を締結させられるという効果はありませんが、不法行為として損害賠償請求の対象となることはあります。
2.「募集・採用に当たり、「50歳未満」を対象とすること」について
労働施策総合推進法9条は、募集及び採用において年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと規定しています。
したがって、50歳未満を採用の対象とすることは、同条に違反します。同条に違反する行為に対しては、行政上の助言、指導、勧告等の公法上の効果が定められていますが、さらに、同条違反の行為が不法行為となり損害賠償請求の対象となることが考えられます。
3.以上のとおり、募集・採用に当たり、「女性のみ」を対象とすること、「50歳未満」を対象とすることは、均等法や労働施策総合推進法に違法するので、避けるべきです。
出向
Q17 役員出向
・当社の社員AをB社に、取締役として出向させたいと考えていますが可能でしょうか。
・可能な場合、どのような手続が必要で、どんな問題が想定されるでしょうか。
A17
貴社は、社員Aの同意を得て、AをB社の取締役(役員)として、出向させることは可能です。
手続として、①貴社とAとの間に出向に関する契約が必要、②貴社とB社との間で出向の内容に関する契約が必要です。
<解説>
1.出向の意義
出向とは、労働者が使用者(出向元)との労働契約を維持しつつ、長期にわたって他企業(出向先)の指揮命令に服して労働することをいいます。
2.出向の根拠
事前の同意(採用時を含む)や就業規則に業務上の必要性に応じて出向を命じる旨の定めがあること、その中若しくはその他の規定で、出向先の労働条件・処遇・出向期間・復帰条件等が整備され、内容的にも著しい不利益を含まないことがないことが必要です。
3.役員としての出向
役員(取締役)としての出向は、出向先との間で委任契約を結ぶ必要があり、役員(取締役)として責任(忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限等)が加重されます。そのため、出向元との労働契約上予定された出向とはいえません。
4.貴社と社員Aとの間の出向に関する契約の締結
したがって、貴社は、前記の就業規則の出向に関する規定等の存在を根拠に社員AをB社に役員(取締役)として出向させることはできません。貴社は社員Aに役員(取締役)として責任が課せられることを説明したうえで、社員Aが貴社に在籍したまま、B社に役員(取締役)として出向することの個別的な同意を得て、出向に関する契約を締結することが必要です。出向期間や貴社の業務を休職するのか、給与をどうするかの合意も必要です。
5.貴社とB社との出向に関する契約の締結
貴社と社員Aとの間の出向に関する契約を実現するためにも、B社との間で、出向に関する具体的な内容を合意しておくことが必要です。
Q18 出向後の労働条件
・当社の社員AをB社に出向させたいと考えています。
当社では、時間単位の有給休暇の取得が可能ですが、B社にはその制度がありません。出向は可能でしょうか。
・また、社員Aは、当社に時間単位の有給休暇の取得を請求できますか。
A18
B社への出向は可能です。
社員Aは出向元に時間単位の有給休暇の取得を請求できません。
<解説>
1.出向後の労働条件
出向とは、労働者が使用者(出向元)との労働契約を維持しつつ、長期にわたって他企業(出向先)の指揮命令に服して労働することであり、1個の労働契約を構成する権利義務が出向元と出向先に分割され、出向元、出向先と労働者間に二重の労働契約が成立します。
出向先に指揮命令権が移るので、労働契約は出向先に労働義務を負います。労基法等の適用は現実の就労関係に即して判断されますから、労働時間、休日、休暇等は実際に労務を提供する出向先の労働協約や就業規則によることになります。
2.労働条件が出向元より不利益な場合
本件のように出向先の労働協約や就業規則によると労働時間、休日、休暇等の労働条件が出向元よりも不利益になる場合があります。
しかし、出向が他社で就労する形態である以上労働条件が変動することは不可避であること等から、本件でもその合理性は否定できません。
もっとも、出向先での労働条件の変更の程度が著しい場合には、当該出向は権利濫用で無効とされる場合があります。
3.本件の場合
したがって、単に時間単位の有給休暇の制度がないというだけでは、合理性が否定されるとはいえませんが、有給休暇の日数等で不利益を受けることがあれば、労働者は出向元での労働条件が維持されることに期待利益を有していると考えられることから、代償措置として手当等を出向元に請求できると考えて良いと思います。
派遣社員
Q19 派遣社員と懲戒処分
当社が受け入れている派遣社員Aは、取引先の担当者に対してパワーハラスメント行為をして、取引先からクレームを受けました。
・当社は、派遣社員Aに対して懲戒処分をすることは可能でしょうか。
・派遣管理責任者となる当社の管理職Bは、派遣社員Aの行為につき、指導監督を行う責任がありますか。
A19
貴社は、派遣社員Aに対し懲戒処分はできない。管理職Bは指導監督を行う責任がある。
<解説>
1.派遣先の貴社は、派遣社員Aに対して、懲戒処分を行うことができるでしょうか。
本件のように派遣社員Aが派遣先で非違行為を行った場合、派遣社員Aに対し懲戒処分を行うことができる者は、派遣先の貴社か派遣元Cでしょうか。裁判例では、派遣労働者の懲戒処分につき、派遣元の就業規則が適用されて、派遣先の貴社の就業規則は適用されず、懲戒権は派遣元のみが有するとされています(コンピュータ・メンテナンス・サービス事件 東京地判平10.12.7)。派遣先は業務遂行上の指揮命令権を持っていますが、これは労働力の使用収益としての指揮命令であり、それ以上の就業規則違反等に対する懲戒処分(制裁)権限まで含んではいないためです。
2.そこで、貴社が派遣元Cに派遣社員Aの行為につき苦情を述べることで、派遣社員Aの非違行為が派遣元Cに対する就業規則違反となり、さらに貴社に対して迷惑をかけ、派遣元Cの信用を失墜させることにもなるので、派遣元Cは、派遣社員Aに対し懲戒処分を行うことができます。
3.貴社は、事業場につき、秩序維持権及び施設管理権を有しているので、派遣社員Aも貴社の規律には従う必要があります。そこで、貴社は、派遣社員Aが貴社の秩序を乱す行為をした場合には、これを制止し、職場秩序の回復を図る権限を派遣社員Aに対して持っています。
したがって、派遣管理責任者となる貴社の管理職Bは派遣社員Aに対してパワーハラスメント行為を止めさせるための指導監督を行う責任があり、管理職Bの指導監督が著しく不適切な場合には、管理職B自身が懲戒処分の対象となる可能性もあります。
訴訟手続
Q20 労働訴訟と調査嘱託
当社の従業員Aが前雇用主に対し解雇無効確認等請求訴訟を提起していますが、裁判所から当社に対し、調査嘱託によりAの給与に関する照会がありました。
Aからは、調査嘱託に回答しないよう要望されています。
1.当社は、この調査嘱託に回答する義務がありますか。
2.調査嘱託に回答した場合、Aから訴えられることはありませんか。
3.調査嘱託に回答しない場合、調査嘱託を申し立てた前雇用主から訴えられることはありませんか。
A20
・貴社には調査嘱託に回答する公的な義務があります。
・調査嘱託に回答したことを違法な個人情報の提供に当たるとしてAから訴えられることはありません。
・調査嘱託に回答する公的な義務に違反しても、直ちに前雇用主に対する不法行為となるものではありませんが、不法行為となる場合もあるので注意が必要です。
<解説>
1.調査嘱託の理由
前雇用主に解雇されたAが解雇無効の判決を得て原職復帰する場合、解雇から無効判決までの間の賃金は、その間労働契約が存続していたものとされ、前雇用主には、解雇による就労不能につき原則として「責めに帰すべき事由」があるとされることから、Aは、前雇用主に対し解雇期間中の賃金請求権を失いません。
ただし、Aは解雇されてから解雇無効判決までの期間に貴社で働いて収入を得ていますので、前雇用主はこの中間収入をAに遡及支払いする賃金額から控除できるかが問題となります。
結論として、Aは解雇期間中の平均賃金の6割までは遡及賃金の支払を確保されますが、それを超える解雇期間中の賃金は中間収入控除の対象となります。
2.調査嘱託とは、裁判所が申立て又は職権で、事実あるいは経験則に関して、必要な調査を官庁もしくは公署等その他の団体に嘱託することができる、一種の職権証拠調べです。したがって、前雇用主は、控除できる中間収入額を知るために貴社を照会先として調査嘱託申し立てることができます。
3.貴社は調査嘱託に回答する義務があるでしょうか。
判例(大阪高判平19.1.30)は、「調査嘱託を受けた者は、弁護士会または裁判所に対し、報告を求められた事項につき報告すべき公的な義務を負う」としています。ただし、回答しなかった場合でも罰則はありません。
4.調査嘱託に回答した場合、Aが個人情報を違法に提供したとして損害賠償を請求できないかが問題となります。
Aの給与に関する情報は個人情報ですから裁判所への提供は第三者提供にあたります。よって、本来は、Aの同意なく第三者提供できないことが原則です。
しかし、調査嘱託による個人情報の提供は、法令に基づくものであり、本人の同意なく第三者に個人情報を提供できる例外的な場合にあたります。
したがって、貴社が裁判所へAの給与に関する報告をしたしとても違法とはいえず、貴社が責任を問われることはありません。
5.逆に、貴社が、Aの給与に関する報告を提出しない場合、調査嘱託を申し立てた前雇用主から責任を問われるおそれはあるでしょうか。
前記のとおり、貴社の回答義務は、裁判所に対する公法上の義務で、調査嘱託を申し立てた当事者(ご質問では前雇用主)に対する義務ではないことから、公法上の義務に違反したことから直ちに当事者(前雇用主)に対する不法行為となるものではありません。判例(東京高判平24.10.24)も同旨です。
しかし、同判決は、「調査嘱託を受けた者が、回答を求められた事項について回答すべき義務があるにもかかわらず、故意又は過失により当該義務に違反して回答しないため、調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者の権利または利益を違法に侵害して財産的損害を被らせたと評価できる場合には不法行為が成立する場合もあると解するのが相当である。」としていることに注意すべきでしょう。
労働組合
Q21 経費援助
当社は、プロ野球や大相撲の年間予約席を利用する権利を有しており、通常は、取引先などを招待し、販売活動につなげる目的で利用しています。
これらの予約席は1回当たりでも相当な金額となりますが、今回、当社が、企業内労働組合に対し予約席を無償で使用させる場合、どんな問題があるでしょうか。
A21
労組法7条3号後段の「経理上の援助」に該当して、不当労働行為となるおそれがある場合と例外的に許容される場合があります。
<解説>
1.労組法7条3号は、支配介入のほか「労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を不当労働行為として禁止しています。 労働組合を運営するための経費は労働組合自らが負担すべきであり、会社から経済的利益を受けることで、労働組合の自主性を損なうおそれがあるためです。
2.そこで、不当労働行為となるおそれの強い例として、次のような場合があげられます。
例えば、会社が、企業内組合の書記長や副委員長を予約席に招待したことが、企業内組合の上部団体への加入を阻止するための利益誘導に当たると判断されるような場合です。
このような場合は、労働組合の自主的な運営を妨げる恐れが認められるため、不当労働行為の成立が認められます。
3.これに対して、労組法7条3号は、労働組合の実態を考慮して、次のとおり、経理上の援助が不当労働行為には該当せず、例外的に許容される場合を定めています。
①労働時間中の労使協議や団体交渉につき賃金をカットしないこと
②組合の福利厚生その他の基金に対する使用者の寄付
③最小限の広さの組合事務所の貸与
4.経理上の援助が不当労働行為として禁止されるのは、労働組合の自主性を損なうおそれがあるためですから、実質的に自主性を損なわないものは該当しないと考えられます。そこで、労働組合が組合員のために予約席を無償で使用させることを交渉し、これを勝ち取ったような場合は、労働組合の自主性を損なうこともなく、②の福利厚生に対する会社の寄付とも解釈できることから、不当労働行為とはならず許容される場合に当たると考えます。
副業
Q22 社内副業
最近、社内副業が話題となっていますが、どのような制度でしょうか。
当社と従業員間の契約関係に異動を生じるのでしょうか。
A22
所属部署の業務と他部署の業務に従業員の就業時間を振り分けて働くこと(社内副業)が認められる制度で、社内副業に雇用契約とは別の契約関係が生じる場合もあります。
<解説>
1.最近、社内副業というものが盛んになってきているようですが、その内容は 会社によりさまざまです。
社内副業の定義は、明確ではありませんが、本業の所属部署の業務と他部署の業務に従業員の就業時間を振り分けること、所属部署以外の部署で働くことが認められる制度となります。例えば、営業部所属の従業員が労働時間の一部につき制作部で働くということです。本業の所属部署の15%程度の労働時間が社内副業に振り分けられているという会社もあります。
2.社内副業に対して報酬・賃金を支払うかどうかも会社によってさまざまです。
賃金を支払う会社もあれば、労働時間の振り分けにすぎないから支払う必要はないと考える会社もあります。
賃金と働き方(労働時間の配分)は区別して、全体の労働時間により会社は賃金を支払っていると考えると、社内副業の場合も別途賃金を支払う必要はないと考えられます。もちろん、社内副業が時間外労働に該当することになれば、時間外割増手当の支払は必要となります。
3.しかし、社内副業には、労働時間の振り分けだけでは処理できない場合も想定されます。例えば、外国人IT技術者が、休日に社内副業として外国語の講師をするような場合です。休日は本来自由な時間ですし、外国語の講師は、本来業務とは別の業務ですから、労働契約により規制することは困難です。
同一人が、副業として休日に他社で外国語の講師をした場合、他社との間には業務委託契約が締結されます。そうであれば、自社での講師の場合でも他社と同様に副業として扱い、業務委託契約を締結して、委託料を支払うことが必要となると考えます。
懲戒
Q23 降格と二重処罰の禁止
当社は、店長であるAが重大な過失により当社に多大な損害を与えたことから、店長の資質がないと判断して、副店長に降格しました。副店長に降格されると就業規則に規定される店長手当月額3万円は支給されなくなりますが、基本給に変更はありません。
他方、重大な過失により会社に多大な損害を与えたことは、就業規則の懲戒事由に当たることから、懲戒処分として、Aをけん責処分とすることを検討しています。しかし、就業規則では降格に関する規定が懲戒処分の項目にしかないことから、降格させたAをけん責とすることは二重処罰とならないか心配しています。懲戒処分は可能でしょうか。
A23
降格は、人事権の行使として有効に行われている。懲戒処分としてのけん責も懲戒事由に該当し、適正な手続きにより行われたものである。
したがって、懲戒処分としてけん責処分することは二重処罰に当たらない。
<解説>
1.降格の定義
降格とは、役職(職位)または職能資格、資格等級を低下させることを言います。そして、降格は、人事権の行使として行われるものと、懲戒処分として行われるものがあります。
2.人事権の行使としての降格
そのうち、役職を低下させるにすぎず、職能資格や資格等級の低下を伴わないものは、労働力配置の問題であり、職務適性の欠如や成績不良などの業務上の必要性があり、権利濫用等に当たらなければ、会社はその裁量で行うことができます。その根拠として、会社が人員配置を裁量により決定できることが労働契約の内容となっていることがあげられます。
なお、職能資格や資格等級を低下させる降格は、資格や等級と直結している基本給の変更をもたらすことから、就業規則上の規定や労働者の同意など契約上の根拠が必要となります。
3.懲戒処分としての降格
これは、企業秩序違反行為に対する制裁罰である懲戒処分として降格がなされるものです。したがって、懲戒処分に関する厳格な規制に従う必要があります。
4.「企業秩序違反」と「職務適格性を低下させるもの」である場合
このような場合、企業秩序違反行為に対する懲戒処分を行うとともに、適格性の低下等を理由に人事権の行使としての降格を行うことは、それぞれの要件を充たす限り可能です。
5.結論
本件の店長から副店長への降格は、業務上の必要からなされたもので、基本給の変更をもたらすものではなく、役職の低下に過ぎませんから、人事権の行使として会社の裁量で行うことが可能です。権利濫用となる事情もないと考えます。したがって、本件降格は人事権の行使によるもので、懲戒処分ではありません。
次に、当該行為が就業規則に規程された懲戒事由に該当する場合、適正な手続きにより、懲戒処分をすることは可能です。
本件では、店長の行為を企業秩序違反行為であるとして、就業規則に従い、けん責としたもので、二重処罰には当たりません。
6.参考判例
L館事件 最一小判平成27.2.26 労判1109-5
上告人会社は,社員である被上告人らがそれぞれ出勤停止処分を受けたことを理由に,資格等級制度規程に基づき,被上告人らをそれぞれM0からS2に1等級降格した。同規程には降格事由の一つとして就業規則46条に定める懲戒処分を受けたことが規定されていた。判決は,被上告人らに対する各出勤停止処分は有効であるから,被上告人らについては降格事由に該当する事情が存するものとした。
また,資格等級制度規程は,社員の心身の故障や職務遂行能力の著しい不足といった当該等級に係る適格性の欠如の徴表となる事由と並んで,社員が懲戒処分を受けたことを独立の降格事由として定めているところ,その趣旨は,社員が企業秩序や職場規律を害する非違行為につき懲戒処分を受けたことに伴い,秩序や規律の保持それ自体のための降格を認めるところにあるものと解され,現に非違行為の事実が存在し懲戒処分が有効である限り,その定めは合理性を有するものということができるとして,被上告人らが,管理職としての立場を顧みず,職場において女性従業員らに対して本件各行為のような極めて不適切なセクハラ行為等を繰り返し,上告人の企業秩序や職場規律に看過し難い有害な影響を与えたことにつき,懲戒解雇に次いで重い懲戒処分として前記のとおり有効な出勤停止処分を受けていることからすれば,上告人が被上告人らをそれぞれ1等級降格したことが社会通念上著しく相当性を欠くものということはできず,このことは,上記各降格がその結果として被上告人らの管理職である課長代理としての地位が失われて相応の給与上の不利益を伴うものであったことなどを考慮したとしても,左右されるものではないというべきである。
以上によれば,上告人が被上告人らに対してした上記各出勤停止処分を理由にする各降格は,上告人において人事権を濫用したものとはいえず,有効なものであるというべきであるとしました。
高齢者
Q24 継続雇用制度と労使協定による選定要件について
A社は、平成16年に60歳定年後の65歳までの高年齢者の継続雇用措置を導入しました。
平成23年にA社は労使協定により、継続雇用者を選定する要件も定めました。そこには、「定年退職前5年間に減給以上の懲戒処分を受けていないこと」との定めがありました。
Xは、令和7年2月末日定年退職となりますが、昨年、減給の懲戒処分を受けました。
Xは、継続雇用を希望していますが、A社は、Xを継続雇用しなければならないでしょうか。
A24
高年齢者雇用安定法改正法附則3項で、労使協定による継続雇用者の選定の制度は令和7年3月31日まではその効力を有するとした経過措置が定められています。
そこで、現在でも、その選定要件による人選は有効です。
したがって、A社は、Xが要件を充足しないことから、Xを継続雇用しないことは可能です。
<解説>
平成24年に高年法の改正で労使協定による継続雇用者の選定の要件が廃止されました。
そこで、継続雇用者の選定に関しては、心身の故障のため職務をとることができない者や勤務状況が著しく不良で従業員としての職責を果たせないこと(解雇事由がある者)以外は、希望者全員を再雇用することが求められることになりました。
ただし、継続雇用者の選定の要件を定める労使協定が、平成24年の高年法の改正以前に締結されたものであれば、この要件は、2025年(令和7年)3月31日まで有効との経過措置が定められました(高年齢者雇用安定法改正法附則3項)。
継続雇用を希望するXは、定年退職前5年間に減給以上の懲戒処分を受けていることから、継続雇用者となる「要件」を満たしていないことになります。
したがって、A社は、Xが継続雇用者の選定要件に合致していないことから、継続雇用しないことが可能です。
賃金【NEW】
Q25 賃金差押えの禁止【NEW】
賃金差押えの場合に、差押えの対象とならない項目はあるでしょうか。
通勤交通費や健保給付金、社員紹介料はどうでしょうか。
A25
社員に支払われる金銭の中には、差押えの対象にならないものがあります。
<解説>
1.賃金債権の差押え
国税徴収法や民事執行法に基づき賃金が差押えられた場合、使用者が行政官庁や差押債権者に賃金を支払っても、労基法上、直接払原則に反しないとされています。但し、労働者の生活保障の趣旨から、国税徴収法や民事執行法に基づく賃金の差押えには、差押え限度額がありますし、差押えの対象とならない金銭もあります。
2.通勤交通費
労基法上、通勤交通費は本来労働者が負担すべきものですが、支給要件が就業規則などで定められているときは賃金に当たるとされます。すると、民事執行法に基づく賃金の差押えの場合、通勤交通費は差押えの対象となることになります。
しかし、実務上、債権差押目録において、毎月の給料(基本給と諸手当。ただし、通勤手当を除く。)とされていることから、実際は差押えの対象とはされていません。
税金の差押の場合に、通勤交通費が差押の対象となるか否かですが、旭川地裁平成27.7.21判決が、通勤費は国税徴収法76条1項本文柱書の「これらの性質を有する給与」に当たる、つまり差押えが可能であると判示しています。
3.健康保険給付金
健康保険では、業務外で発生した病気やけが、または、出産および死亡した場合に定められた給付金が支給されます。具体的には、療養の給付、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料などです。
この給付金は、給与に含まれて支給されますが、健康保険法61条は、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」と規定して、健康保険給付金の差押えを禁止しています。
4.社員紹介料
社員の紹介により顧客との間で商品の売買取引が成立した場合に支給される紹介料が、恩恵的に支払われていれば、原則として賃金に当たらないので差押の対象となりませんが、予め支給要件が定められていて、会社に支払い義務があり、支給が保証されている場合は給料となるので、差押の対象となります。